楽天証券は、国内で最初にクレジットカードによる投資信託買い付けサービスを開始し、業界のポイント付与競争の火付け役になった証券会社です。
ところが最近、楽天証券のポイント制度は少しずつ条件が悪くなり、複雑化しましてしまいました。
しかし、私のように楽天証券で楽天ポイントをタダ取りしている身からすると、むしろ条件が良くなりました。
そこで本記事では、楽天証券のポイント制度を改めて整理し、毎月1000ポイントタダ取りするワザをお教えしたいと思います。
ポイント制度改悪の背景
楽天系のサービスはポイント制度が魅力的です。
楽天証券もその一つで、ポイント制度に惹かれて使っている方も多いと思います。
楽天ユーザーは、ポイント制度に敏感で、うまく賢く使い倒すイメージがあります。私もそんな人の一人です。
ですが2022年2月、楽天グループの決算説明会で三木谷社長から次のような説明がありました。
「(楽天証券のポイント還元は)少し寛容すぎるところがあった。お客様の中には我々の利益に貢献してくださらない方もいる。そこで顧客ごとに分析を始めた。ポイントのコストが多くかかっており、そこを変える。簡単に言うと通年で70〜80億円の話になる」
これまではさすがに大盤振る舞いすぎたようですね。
というこで、楽天証券のポイント制度は大きく変わりました。
これまでたくさんポイントを貰えていた人が、必ずしもポイントを貰えるような制度ではありません。

現在のポイント制度
概要
それでは、楽天証券のポイント制度はどのように変わったのでしょうか。
| これまで | これから | |
| 楽天カードによる投資信託購入 |
一律1% 上限50,000円 獲得上限500pt |
(2022年9月買付分以降)
0.2%もしくは1% 上限50,000円 獲得上限500pt |
| ハッピープログラム |
投資信託の保有額10万円ごとに毎月3~10pt(保有商品による) |
(2022年4月以降)
毎月末に投資信託の保有額がはじめて一定額を超えたらポイント獲得(楽天証券リンク) →実質消滅 |
| 楽天キャッシュによる購入 | なし | (2022年8月以降)
楽天キャッシュによる投信積立(上限50,000円)が可能に 楽天カードから楽天キャッシュにチャージすることで0.5%のポイント付与 (2022年8月~12月) 上記+0.5%(合計1%)のポイント付与 |
それぞれ解説していきます。
楽天カードによる投資信託購入
ここが改悪といわれる所以です。
これまで、楽天カードによる投資信託の購入は、50,000円を上限として、一律1%(上限500pt)が付与されていました。
2022年9月買付分以降、楽天カードによる投資信託の購入は、50,000円を上限として、0.2%もしくは1%(上限500pt)が付与されることになります。
0.2%、1%どちらになるかは、購入した投資信託によります。
ざっくりいいうと、手数料が高く資産形成に使えないような商品(笑)には1%のポイントが付与され、手数料が低く資産形成の味方になるような商品には0.2%のポイントしか付与されません。
ざっくりではなく正確にいうと、信託報酬のうち販売会社が受け取る手数料(代行手数料)が年率0.4%(税込)以上の商品には1%のポイントが付与され、信託報酬のうち販売会社が受け取る手数料(代行手数料)が年率0.4%(税込)未満の商品には0.2%のポイントが付与されます。
「信託報酬のうち販売会社が受け取る手数料」であって、単に「信託報酬」でないことに注意してください。(ふつう、なかなか「信託報酬のうち販売会社が受け取る手数料」を気にして投資信託を買う人はいません・・・)
個々の商品が0.2%と1%のどちらになるかは、楽天証券のホームページをご覧ください。投資信託の手数料は変わっていくものなので、このリストも変わっていきます。
私のブログを読まれるような、自分でいろいろ調べて投資する方が選ぶ投資信託は間違いなく0.2%の商品になってしまいます。
ハッピープログラム
これまではハッピープログラムにより、投資信託の保有額10万円ごとに毎月3~10pt(保有商品による)が付与されていました。
小さいポイントのように思われるかもしれませんが、資産運用を長期にわたって続けて、保有額が数百万を超えると大きな意味を持ってきます。逆に言うと、数十万の資産規模では大きな意味を持ちません。
2022年4月、この制度は大きく改悪され、保有額がはじめて一定額を超えた際にポイントが付与されることになりました。
詳しくは楽天証券のホームページをご覧いただきたいのですが、ポイント付与は次のとおりになっています。
| 基準保有額 | 進呈ポイント |
|---|---|
| 月末時点の保有額が、はじめて10万円に到達した場合 | 10ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて30万円に到達した場合 | 30ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて50万円に到達した場合 | 50ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて100万円に到達した場合 | 100ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて200万円に到達した場合 | 100ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて300万円に到達した場合 | 100ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて400万円に到達した場合 | 100ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて500万円に到達した場合 | 100ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて1,000万円に到達した場合 | 500ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて1,500万円に到達した場合 | 500ポイント |
| 月末時点の保有額が、はじめて2,000万円に到達した場合 | 500ポイント |
例えば、ある月にはじめて保有額が10万円を超えると10ptもらえます。しかしその後、保有額が5万円になって、そこから回復して再び10万円になってもそのときはポイントをもらえません。
この制度はもうなくなったと思ってもよいくらいのレベルです。
ただし、後述する「ポイントタダ取り」勢からすると、もともと活用していなかった制度なので、あまり問題はありません。
楽天キャッシュによる購入
これまでは、楽天キャッシュで投資信託を購入できませんでしたが、2022年8月以降、50,000円を上限として、楽天キャッシュで投資信託の積立ができるようになりました。
50,000円の購入枠は、楽天カードの購入枠(各月50,000円)と別なので、合計すると月100,000円積み立てできます。
投資に限らず、楽天カードにより楽天キャッシュにチャージすると、0.5%のポイントが付与されます。

毎月1000ポイントタダ取りする
ポイント制度は、楽天証券ユーザーはもちろん、ユーザーでない方も恩恵にあずかれます。
かくいう私もSBI証券がメイン口座なので、楽天証券はポイント取りをするだけです。
ではどうすればよいのか。
積み立てで買って、毎月売って現金化すればよいのです。
そうすれば毎月1000ポイントをタダ取りできます。
クレジットカードによる積み立て
2022年8月まではどの投資信託を買っても1%のポイントが得られますが、9月以降は1%もしくは0.2%になってしまいます。
おそらく大部分の方がこれまで購入していたのは0.2%のポイント付与になるはずです。
いまのうちから1%のポイントが貰える商品に切り替えましょう。
また、「ポイントタダ取り作戦」では、投資信託を買ってすぎに売ります。投資信託には、購入時と売却時に手数料が発生する商品があるので、それも避けるようにしましょう。
整理すると、購入すべき投資信託の条件は次のとおりです。
① 信託報酬のうち販売会社が受け取る手数料(代行手数料)が年率0.4%(税込)以上
② 買付手数料と信託財産留保額(売却時の手数料)が0
③ 値動きが小さい
上記の①と②は必須。できれば③であってほしいというところです。
①でないと得られるポイントが小さくなってしまいます。
②でないと投資信託の売買に余分なコストがかかってしまいます(②であれば売買にコストは発生しない)。
③でないと、購入から売却までの間に値動きして損失が発生することがあります(もちろん同じくらいの確率で利益が発生しますが)
私自身、この条件でファンドを選びました。
そしてこれだ!と思えるものを見つけました。
|
大和アセットマネジメント 買付手数料、信託財産留保額 0 信託報酬 年1.1% 運用方針: 複数のマザーファンドを通じ、値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資。安定資産とリスク資産に区分し、両資産の配分を調整、基準価額の変動を抑えた運用をめざす。また、定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を引き下げ、さらなる基準価額の下落を抑制する。 |
信託報酬が年1.1%は、資産運用に使うファンドとしては高額です。しかし年1.1%ということは、1日あたりでいうと0.003%です。
買ってからすぐ売る使い方ですと、信託報酬が大きな問題ではありません。
バランスファンドなので、株式インデックスよりは変化が小さいです。そのため、購入から売却までの間に急落するリスクが小さいです。
自分で調べるのが面倒な人は「堅実バランスファンド -ハジメの一歩-」を選べばいいと思います。
楽天キャッシュによる積み立て
楽天キャッシュによるポイント付与には、クレジットカード積み立てのようなファンドの条件がありません。
そのため、購入すべき投資信託の条件は先ほどよりは一つ項目が少なく、次のとおりです。
① 買付手数料と信託財産留保額(売却時の手数料)が0
② 値動きが小さい
この条件で選ぶなら、この投資信託を買っておけば間違いありません!
|
三菱UFJ国際投信 買付手数料、信託財産留保額 0 信託報酬 年0.132% 運用方針: 「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として国内の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。 |
ガチガチの手堅い値動きの投資信託です。購入から売却までの間にほぼ値動きしません。
信託報酬も安く、資産運用の一角に組み入れることもあり得る投資信託です。
これを買っておけば間違いないのですが、私は違う選択をしました。
私はあくまで「ポイントタダ取り」なので、毎月の購入後、投資信託を売却します。
楽天カードと楽天キャッシュによる積み立てで商品が異なると、売却操作が少し手間が増えます。
そこで私は、楽天キャッシュでは、楽天カードと同じ投資信託を購入することとし、毎月の手間(たぶん1分くらい)を削減することにしました。
ということで、私の場合、楽天キャッシュで購入する投資信託は次のとおりです。
(前述)
|
大和アセットマネジメント 買付手数料、信託財産留保額 0 信託報酬 年1.1% 運用方針: 複数のマザーファンドを通じ、値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資。安定資産とリスク資産に区分し、両資産の配分を調整、基準価額の変動を抑えた運用をめざす。また、定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を引き下げ、さらなる基準価額の下落を抑制する。 |

毎月のスケジュール
毎月のルーチン
「ポイントタダ取り」は、一度設定してしまえば、毎月の作業は5分もかかりません。
クレジットカードによる投資信託購入の流れ
① 申し込みの締切 :前月12日
② 購入日 :当月1日もしくは8日
③ 売却・楽天銀行へ入金:当月2~26日
④ カード支払い日 :当月27日
詳細はリンクをご覧ください。
楽天キャッシュによる投資信託購入の流れ
① 支払日 :前月13~15日
② 購入日 :任意
③ 売却・楽天銀行へ入金:当月2~26日
④ カード支払い日 :当月27日
購入日は楽天カードによる購入とそろえて1日にしておくとよいと思います(その方が売却などの管理が楽です)。
楽天キャッシュの支払日に購入金額がチャージされている必要があります。
ふつうにやると楽天キャッシュの残高管理が面倒ですが、楽天キャッシュには「残高キープチャージ」という設定があります。
例えば「残高キープチャージ」を5万円で設定しておくと、残高が5万円を下回ると自動的に楽天カードで楽天キャッシュにチャージされます。
楽天キャッシュによる投資信託の購入をしたい人は、設定しておくとよいと思います。
詳細はリンクをご覧ください。
ポイントタダ取りの元手
ポイントタダ取りをする際に、カード引き落としが投資信託の売却でお金を得るより「後払い」であれば元手がいりませんし、「前払い」であれば元手がいります。
細かい話をすると、楽天カードによる楽天証券のポイントタダ取りは元手がいりません。
なぜならば、当月1日または8日購入分のカード引き落とし日は27日なので、購入日から引き落としまでの間に投資信託を売却し楽天銀行に送金すれば、売却代金でカード支払いを賄えます(下落して若干損をしてしまう場合もありますが)。
そして、もっと細かい話をすると、楽天キャッシュによる楽天証券のポイントただ取りは元手がいる場合といらない場合があります。
楽天キャッシュの積み立ては前払いです。前日13~15日の引き落としにそなえて前月12日に所定金額がチャージされている必要があります。
例えば前月1~11日に楽天カードで楽天キャッシュをチャージするならば、次月27日にその代金が引き落とされます。この場合、27日までに投資信託を売却して楽天銀行に送金すれば、実質的には「後払い」になるため、元手がいりません。
一方でチャージの手間を無くすために「残高キープチャージ」設定をしていると、チャージのタイミングは前月12日ではなく、前々月の楽天キャッシュが引き落とされた前々月12日になります。そうすると、カード引き落としは前月27日になるので「前払い」。すなわち元手がいります。
毎月の作業
先ほど、クレジットカードと楽天キャッシュによる投資信託の流れを整理しましたが、一度設定してしまえば、①、②、④は自動的に行われます。
実質的な作業は、「③売却・楽天銀行へ入金」だけです。
さらにいうならば、楽天証券から楽天銀行への入金も自動でできるので、実質的な作業は、毎月2日~20日くらいの空いた時間に投資信託を「売却」するだけです。
スマホで数分の作業です。
マネーブリッジで手間を減らす
楽天証券で投資信託を売却すると、証券口座に現金が貯まります。
一方、クレジットカードの引き落としは楽天銀行になります。
そのため、通常は証券口座から楽天銀行へ送金が必要になります。しかし、毎月売却したりしていると、送金作業も面倒です(売却操作をしてから現金化される数日の間に、現金化したことを忘れたりもしますし・・・)。
しか~し、楽天証券と楽天銀行には、マネーブリッジという機能があります!
これを使うと楽天証券で売却して得た現金を、楽天銀行に自動的に送金できます。
「ポイントタダ取り」には、非常に便利なツールです。
ポイントの使い道
「ポイントをゲットしても使い道に困るんじゃないか・・・」
そんな心配はありません。
楽天では、使い道が広い「通常ポイント」と期間と使途が限定される「期間限定ポイント」というものがあります。
クレジットカード及び楽天キャッシュによる投資信託の積み立てで得られるポイントは、通常ポイントです。
通常ポイントは投資信託の購入に使うことができ、クレジットカード購入する際に、ポイントを消費することができます。
たとえば、50,000円のクレジットカード積み立てだとして、購入時に楽天の通常ポイントが1,000pt貯まっていれば、1,000pt消費し、カードの引き落としが49,000円になります。(その際に得られるポイントは490ptになります)
つまり、クレカ積み立てをする限り、楽天ポイントの使い道に困ることはありません。
おわりに
本記事では、毎月たった数分の手間で楽天ポイントを1000ポイントタダ取りする方法を解説しました。
そして貯めたポイントは資産運用に使えます。
長い目で見ると資産運用は、こうしたほんの些細なことが最終的に大きな違いを生み出します。
だれでもできることなので、ぜひ参考にしてみてください。
ただ、冒頭に紹介したように、三木谷社長は、
「(楽天証券のポイント還元は)少し寛容すぎるところがあった。お客様の中には我々の利益に貢献してくださらない方もいる。そこで顧客ごとに分析を始めた。ポイントのコストが多くかかっており、そこを変える。簡単に言うと通年で70〜80億円の話になる」
と言っています。
私が紹介した方法は間違いなく、残念ながら、楽天グループの利益に貢献しません。
あまりに多くの方が、こうした効率的なポイント取得をしていると、また取り締まられるかもしれません(笑)。
この記事を見た人は、こっそりと・・、がっつりポイントを稼いでください。








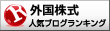

あれ? 楽天カードって支払いにポイントを充当しても還元されるポイントが減らないってのがウリのひとつだったはずですけど、もしかしてこの点も遂に改悪されたんですか?
本文で述べた例ですと、50000円分の投資信託を買うために、1000ポイント使い、49000円カードで支払うので、カードの利用額は49000円です。
ポイントはカードの利用額49000円の1%になります。
私の実績としてもずっとこのようにポイントをもらっています。